RECORD #02男性らしくはない、女性らしくもない
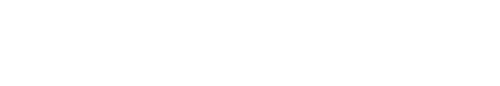
仕事関係の飲み会に参加した後に、酔ってほてった顔を夜風で冷ましながら、ひとり駅まで歩いていく時間が、好きだけれど苦手だ。
私は人と話すのは得意ではないけれど、お酒を介してであれば、誰とでもそれなりになごやかに会話を交わせる自信はある。
ただし、仕事でしか接点のない人とは、さすがに昔からの友だちのように心を開いて何でも話せるというわけではない。相手の関心に寄り添えるように、私からの一方的な話にならないように、慎重に話題を選ぶ。そして、お開きになった後はいつも、うまく話せていたかな、余計なことを言ったりしてないかな、私、気が遣えないからな……などと、頭の中でぐるぐると反省する。
そうやって自分のコミュニケーション能力不足に落ち込みながら、ひとりでぼうっとビルとビルの合間に浮かぶ月を見上げていると、この瞬間が、人生で一番孤独を感じる瞬間であるように思われてくる。
自分が心を開ける人間なんてこの世にはいない。たとえどれだけ交友関係を広げたとしても、仲の良い家族が帰りを待っているとしても、本質的には私は一生「ひとり」である……次々と湧いて来る孤独感を振り払うように、早足で駅に向かう。コンビニで適当に買った缶チューハイを手に、改札前の柱に寄りかかってこっそり追い酒をしながら終電を待つ。
昔からの地元の友だちとふたりで飲みに行った帰りには、こんなことを考えなくて済んだのに、と思う。
首都圏に住んでいたり、仕事が忙しかったりしてせいぜい半年に一回くらいしか会えず、でもその間もどうか彼女たちが幸せであれ、と思いを寄せるような、数少ない友だちたち。各々の話したいことを話したいだけ話しても、お互いが楽しく過ごせて、いっしょに終電に乗って片方が最寄り駅で降りるまでのぎりぎりの時間さえ惜しむほど、話の尽きない友だちたち。
すべての人間関係がそのようにあればいいのに、世の中はなかなかうまくいかない。
そうして考えこんでいるうちに、私はふと、突飛な妄想に至る。
もし、私が男性だったら、もしくは同性愛者だったら、同性の友だちたちの誰かと恋人になっていたのだろうか、と。
あるいは、過去の恋人たちや、かつて学校やSNSで親しくなったけれど今はほとんど連絡を取っていない男性たちとも、友だちとして関係を続けられていたのだろうか、と。
2016年、ファンに惜しまれつつ57歳で亡くなった漫画家、吉野朔実は、私の人生に大きな影響を与えてくれた作家のひとりだ。
中学生のころに『少年は荒野をめざす』を読んでから、ずっとすごい漫画家だと思ってはいたが、大学時代の文学系サークルの先輩でライターの青柳さんが「あらゆることはあらかじめ吉野朔実『恋愛的瞬間』に書いてある」*1と絶賛したことで、やはり彼女は天才だ! とあらためて実感した。吉野朔実の訃報を聞いたのは、それから少し後のことである。できることならもっと、彼女の漫画を読みたかった。ご冥福をお祈り申し上げる。
さて、吉野朔実『恋愛的瞬間』には、「恋愛と友情の違い」の定義について、こんな会話が登場する。
「…恋愛は あらゆる抵抗に打ち勝つ相思相愛の力 友情は 相思相愛でありながら 抵抗によって達成できない疑似恋愛関係」
「抵抗?」
「同性であるとか 既婚者であるとか 恋人がいるとか 顔は好みだが性格が気に入らない 性格はいいが肉体的に受け付けない 等々 逆を言えば 抵抗があるにもかかわらず気持ちのベクトルが向き合っている 人間関係と言ってもいい」
「友情は恋愛の一部ですか?」
「そうではないものを私は友情とは呼ばない」
「じゃあ抵抗を克服すれば」
「恋愛になる可能性は極めて高いと言える」
社会人になって間もないころにこのくだりを読んだ時、私はなるほどと思いつつ、あまり自分ごととして考えてはいなかった。しかし、年を経るごとに、より身をもって「友情は恋愛の一部」という言葉を実感するようになっていった。
私と同性の友だちとの関係は、限りなく恋愛関係に近い。私の性自認が女性かつ異性愛者で、それゆえに性的関係には至らない、という一点を除けば。
「抵抗があるにも関わらず好意をお互い向き合い続けて成立させるって、もはや恋愛よりも尊い関係」と佐伯ポインティも評していた*2が、本当にその通りだと思う。孤独でさみしい時に、恋人がほしい、よりも友だちに会いたい、と真っ先に浮かぶのもわけはない。恋愛という大義名分がなければろくに連絡も取らないような異性に対する思いよりも、これまで関係を維持し続けてきた彼女たちへの思いの方がずっと強いのは当たり前なのだ。
とはいえ、半年に一度サシ飲みする、という友だち付き合いだけで孤独をやり過ごせて、恋愛に関することをきっぱりと諦めても生きていけるほど、私が自己完結した人間であればよかったのだが、現実はそうではなく。
友情の延長線上にある、ひとりの人間としての思慕と性愛を両立できる関係……つまりは異性との恋愛への志向を捨てきれずに、結局は男性と女性の境目に関すること、ジェンダーのことについて、私はいまだ思いを馳せ続けているのだった。
私の友だち付き合いは、常に一対一で、複数の友だち同士で集まるということが基本的にない。
そしてそれは、女性同士のグループ、男性同士のグループのどちらにもうまく適合できないことが大きな理由なのだろうな、と推測している。
これは一般論ではなく私の個人的な感覚なのだが、女性同士の3人以上のグループになると、「人間と人間の対話」ではなく、「女性としての共通の話題」になってしまうような気がする。
たとえば、恋愛の話。メイクやファッションの話。「推し」の話。女性同士のコミュニティで無難に会話を回していくための、女性の共通(とされている)事項に関する話題。
私はそうした話題が、どうしても苦手だった。私だって、恋愛やメイクやファッションや「推し」に関する話のネタがないわけでない。でも、私が本当に話したいことはそれではなかった。女性という枠ではなくひとりの人間として、本や、音楽や、映画や、人生のことをもっと話したかった。「女性同士のコミュニティを維持する」という目的のためだけに、数少ない共通事項を必死に引っ張り出してまで、話を合わせるほどの気力はなかった。
私の人生の中で大きな割合を占めている趣味が、一般的に女性が好むとされているものから少しずつずれているのも災いした。
SFやロック音楽が、その代表だった。もちろん、どちらも好きな女性はこの世の中にはたくさんいるだろうが、どう考えても、全員の共通の趣味がない女性同士のあたりさわりのない会話で出していい話題ではない。
さらに、「推し」に対する認識も微妙に食い違っていた。女性の「推し」というと、現実のアイドルや俳優の男性、フィクションの男性キャラクターを連想するが、私はどれもピンとこなかった。私の「推し」は、フィクションの中では少女とか女性のキャラクターであることが多かったし、もっと突き詰めれば、SFの作り込まれた設定や世界観、ロック音楽に織り込まれたカウンターカルチャーそのものが、私にとっての「推し」だった。
重ねて言うが、私は女性と自認している異性愛者で、性的指向としては間違いなくマジョリティ側に属している。
しかし、人生の節々でいまいち女性同士のグループに馴染めない感覚があり、それはつまり、女性性に適合できていない=男性性寄りの性質を持っている、ということなのかもしれなかった。
かと言って、男性同士のグループには適合できるのかというと、それも難しかった。
そもそも、今までの人生において、男性グループ内の親しいやり取りを間近で見た機会が、男性の割合が多かった大学の文学系サークルくらいしかないのだが(それも、正確なサンプルかというと微妙ではあるが)。
フィクション作品の評論、本の蒐集やミリタリーなどのオタク的嗜好、煙草など。女性同士のグループよりは比較的集まる理由がはっきりしており、集まるという手段が目的化していない一方で、下ネタやイジりなどのやや粗雑なコミュニケーションを良しとする……男性同士は男性同士で、独特な連帯方法が存在しているのをそこで知った。
そして、男性グループの楽しげな連帯の中に、女性である私が入っていこうとすると、「俺たちと渡り合えるくらいの知識か、粗雑なコミュニケーションを容認できる度量がないと、名誉男性として受け入れてやらない」というような、目に見えないラインがあるのをどうしても感じてしまった。
断っておくが、サークルの同期、先輩、後輩たちはこれでもまだフェニミズムに理解があって性別の隔たりなく接してくれた方で、私たちより上の世代はもっと女性の排斥傾向が強かった、という風に先輩から聞いている。
私の方が意識しすぎていたのかもしれないが、それでもやはり、まったく意に介さずに男性同士の輪に入っていくのは気が引けた。現実だけではなく、当時の2ちゃんねるやニコニコ動画といったインターネットの場でも、書き込んでいるのは基本的に男性を前提とする暗黙の了解があり、少しでも女性であることを匂わせるや否や輪から締め出して異物扱いする、そんな空気にうっすらと嫌悪感があった。
私は身体的には女性で、異性愛者で、表向きには社会に溶け込んでいるように見える。一方で、精神的には女性らしくもなければ男性らしくもない、ふわふわとした所在なさがあり、その乖離にやはり生きづらさを覚えた。
元彼と別れて自己肯定感がどん底だった時には、やはり彼は私に女性らしさを求めており、私にそれがないのが悪いのか、と本気で悩んだりもした。
もちろん、こうした女性らしさ/男性らしさに関する固定観念が社会から取り払われるように願っているし、現在進行形でジェンダーに関する認識は少しずつ変わってきている。
しかし一方で、女性らしさ/男性らしさが社会を運用していくための機構として、いまだやむを得ず存在している現実も否定できない。男性が出産できるようになるわけでもなし。少なくとも私の生きているうちは、おそらく、ジェンダーはずっと向き合っていかなければいけない問題なのだ。
2021年6月、宇多田ヒカルはインスタグラムのライブ配信中に、さらりと自身が「ノンバイナリー」であることを公表した。
ツイッターでその話題を目にした時、私は彼女がこれまで作り続けてきた音楽と、これまで辿ってきた人生を思って、ああ、そういうことだったのか、と納得がいった。それと同時に、今まで女性らしさ/男性らしさに関して悩んでいたことが、どこか救われるような思いがした。
ノンバイナリーとは、「男性・女性」「彼・彼女」のようなバイナリー(二元論)のどちらか一方にとらわれないすべてのジェンダー・アイデンティティを指す*3。
多くの人の共感を呼ぶ恋愛要素が織り込まれながらも、対象の性別を特定しない歌詞。自身の手でプログラミングを行うなど、細部までこだわりを感じるサウンド制作。女性のジェンダー規範や身体的特徴を強調せず、かと言ってことさらに隠しもしないファッションスタイル。そうした彼女の表現がずっと好きだったからこそ、ノンバイナリーという性自認が背景にあるかもしれないと知って、とてもうれしくなったのだ。
宇多田ヒカルのデビュー当初、私が5歳の時にカラオケで「Automatic」を歌って「10年後は宇多田ヒカルだね」と言われたことがあり、それからずっと、10年先の自分を重ねた存在として意識していたというのもある。
宇多田ヒカルは、二度の結婚と離婚、そして出産を経験している。
ノンバイナリーやその他セクシャルマイノリティの概念を知って日が浅い人は、それって矛盾してない? と思うかもしれない。男性でも女性でもないのに、男性と二度も結婚して、出産までしてるのはおかしくない? と。
それはちがう。絶対にちがう、と、私は言いたい。
私だって、異性と恋愛をしたいし、たとえ困難が待っているとしてもそれでも子どもを産みたいという、身体的な性に端を発した、理性では説明できない欲求はある。
でもそれと、女性らしさ/男性らしさのどちらにもはまりきれない生きづらさは、まったく別の問題だ。結婚して出産しようが、「私は男性と女性のどちらにもあてはまらない」と自認や主張をしたっていい。それはジェンダー、つまりは社会的に形成された性に関することなのだから。人の認識に働きかけることによって「そういうあり方もあるんだ」と受容を促し、いずれは生きづらさを克服していくことも可能なのだから。
とは言え、私もノンバイナリーだ、と宇多田ヒカルのように公表できるほど、はっきりとした確信があるわけではない。
普段の生活で女性として扱われて嫌な思いをしたことは意外と少ないし、正直、女性という属性に甘えてしまっている部分もある。無意識のうちに誰かに女性らしさや男性らしさを強要して傷つけたことだって、ないとは言えない。結局のところ、ある種社会に適合したセクシュアリティだからこそ、今までの人生を安穏と過ごしてこれた節もある。
でも、今後の人生でまた女性らしさ/男性らしさについて悩んだり、多様なセクシュアリティを持った人たちに出会ったりした時に、「どっちかじゃなくていい」と懐を広くして受け止める姿勢は、絶対に忘れないでいたい。
女性らしさ/男性らしさにとらわれない広い視野だからこそ見つけられる、人と人とのすばらしい出会いが、きっとこの先にもあるだろうから。
*1 アオヤギミホコ「あらゆることはあらかじめ吉野朔実『恋愛的瞬間』に書いてある」
*2 佐伯ポインティ「僕がお金持ちになったら、恋愛する予定の人類全員に配りたいマンガ『恋愛的瞬間』 」
*3 エリス・ヤング[著]上田勢子[訳]『ノンバイナリーがわかる本 heでもsheでもない、theyたちのこと』(明石書店)