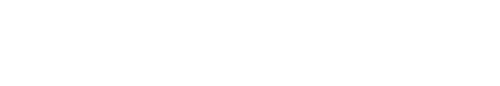自分で言うのもなんだけれど、私はさすがに「普通」ではないと思う。
子どものころから、ずっと「普通」であることや「普通」と見なされていたものをかたくなに拒否し続けてきたから、その事実が古傷のように思考回路の中に残ってしまって、何食わぬ顔して「私は普通です」なんて今さら言えないのだ。
でも、今は「普通」の自覚がある人だって、子どもから今までの成長過程の中で「特別」でありたいと願い、「普通」を拒んだことは多かれ少なかれあるはずだ。そして、どこかで自分は「特別」にはなれないと悟り、あるいは「普通」であることの良さや幸せに気づき、成熟とともに「普通」という社会の大きな流れをうまく乗りこなしていく。
私もいずれそうなると思っていた。小説家になる夢を諦めた大学生の時に「特別」にはなれないと悟り、その後、故郷の富山に帰ってきた時に何気ない日常の中にある幸せに気づき、私も「普通」でありたいと強く願った。
もちろん、この普通/特別問題は誰に限った話ではない。そもそも何を持って「普通」「特別」と定義するのかも含めて人間社会の普遍的な命題で、それ自体「普通」のことだ。
でも、それでも私は自分を「普通」だと言い切ることができない。
日常のふとした場面で自分が「普通」と違う部分にうっすら生きづらさを感じ、なぜ生きづらいのかの理由を本や音楽、映像作品などの他人の創作の中に求め続け、あまつさえ、やはり自分は「普通」ではなく「特別」なのだと確かめたいがために自分自身の創作を欲し、文章に書くような「特別」なことなんて私の人生にはない、という諦めから必死に目を背けながら、こうして絞り出すように文章を書いている。
小学校に上がるころ、私はふと「私がつらいと思っていることを、他の人も同じくらいつらいと思っているのか、それを確かめるすべはない」ということに気づき、絶望した。
いったい何をつらいと思っていたのかは忘れてしまったけれど、確かにそう絶望した瞬間があったことだけは、はっきりと覚えている。そして、その絶望は今も消えることはなく、淡々とした日常の中に、靄のようにうっすらと漂い続けている。
中学生の時、第二次反抗期の波が「特別」への欲求を駆り立てた。
私は同級生と比べて深くものごとを考えているらしい、という優越感と、現実の生きづらさとでばらばらに引き裂かれて、「普通」への反抗はことさら苛烈になった。
好きなミュージシャンの影響と難しそうな本への憧れで泉鏡花や稲垣足穂を読み始め、後に幻想文学に傾倒するきっかけを作ったのもこのころだ。自分は文章を扱うのが得意なのだと確信し、小説家になりたいと思い始めたのも。
高校生の時、文芸部に入部して、実際に小説を書き始めた。
幻想文学に影響を受けた掌編小説をいくつか書き、早熟さをアピールしては他の部員や顧問の先生にちやほやされ、気を良くした。高校二年生の時には全国大会にも行き、私は本当に小説家の才能があるのかもしれない、と自惚れた。
その一方で、小説家を目指すこと以外の選択肢をどんどん排除してしまい、ろくに勉強もせず当然現代文以外の成績はどんどん落ちていった。こんなに本を読んでいるのだから勉強なぞ必要ないと、やはり自惚れがあった。本当に運のいいことに、ちょうど小説家を多く排出している東京の大学の文学部に指定校推薦の枠があり、部活動も評価に入れて推薦してもらってすんなりと進学が決まった。
大学生の時、私は「特別」ではないと思い知り、小説家の夢を諦めた。
小説家を志す者には最高といえる環境に身を置いてみれば、当然ながら上には上がいた。息をするように大量の本を読み、難しい講義も楽しげに自身の血肉としていく人たちの前で、私はやはり視野の狭い井の中の蛙だった。
文芸サークルに所属して始めのころは掌編小説をいくつか書いたけれど、それ以降はぴたりと書けなくなった。そもそも、せめて短編小説ほどの長さを書ききる文章力と構成力がなければ、文学賞の応募も難しかった。
そのうち大学の勉強もついていけなくなって引きこもりになり、在学中に小説家になれなければ生きる価値がない、と自分で自分を勝手に追い込んでいった。このまま消えてしまいたいとも思ったけれど、良好な家庭環境の中で小説家の夢を応援してくれた両親の前でそんな甘えも許されず、結局大学は中退、富山に帰ってとりあえず就ける職を探す、という現実に向き合うことになった。
ウェブデザイナーとして就職した時、私は小説家以外の道でも「特別」にしがみつけるかもしれないと思い、その傍らで、「普通」の生活の中にある幸せにも気づいていった。
始めは、食べてさえいければいいからとりあえずやってみよう、と未経験から飛び込んだ形だったが、この仕事は意外と自分に合っていた。小説を書くための勉強と称して今までインプットしてきた現代アートやミニシアター映画、ロック音楽などのサブカルチャーが、ウェブデザインにも通じる審美眼を自然と磨いてくれていた。就職する前は、自分は勉強ができないからきっと仕事もできないだろうと決めつけていたが、学生時代にそれなりの数の本を読んでいたことで、普遍的に仕事で活かせる文章処理能力や論理的思考能力も身についていたようだ。
一方で、いざ仕事で安定して食べていけるようになり、突出して「特別」な何かにならずともそれなりに社会に適合できるのだとわかると、仲の良い家族がそばにいて、休日にはそれなりに趣味も楽しめる「普通」の生活を送るだけでも十分幸せなのではないか、という思いも強くなっていった。
ふらふらと「普通」と「特別」の間を彷徨う。学生の時の、創作にかけた「特別」への情熱はすっかり冷め、一方で、学生の時から好きな方向性の本や映画やアートや音楽は仕事の合間を縫いつつ細々と追い続ける生活。
中途半端といえば中途半端だけど、本当のところ、自己承認さえできていれば「普通」か「特別」かなんてどちらでもいいし、どちらかである必要もないのだ。なんだかんだその時にやりたいことはできているし、孤独でつらいというわけでもないし、私はこのままでも大丈夫。
2022年1月2日、私は同棲していた彼氏から別れを告げられた。
前からずっと別れたいと言おうと思っていて、なかなか言えなかった。でも、気持ちはもう固まっているし変わらないから、三ヶ月の期限の間に同棲は解消してほしい。
約六年お付き合いし、約二年同棲した相手から淡々と切り出される話を聞きながら、私の本能は半身が引き裂かれるような痛みを全力で訴えている一方で、頭では冷静に、最近の私たちの間にあったことを思い返していた。
私が去年の春に会社を辞め、ほぼ同時期に相手も会社を辞めたこと。私は辞めて間もなく独立したが、彼はぎりぎりまで失業保険で暮らしていきたいと言って、すぐに転職しなかったこと。そちらは働いていないのだからやってくれるだろうという甘えがあり、家事の分担が曖昧なまま放置していたこと。そのような私の気の遣えなさが主な原因で彼が一方的に不満をため、時おり地雷のように爆発し口論する頻度が増えていたこと。以前は私の趣味のミニシアター系映画の鑑賞やギャラリーめぐりにも付き合ってもらっていたが、お互い家にいる時間が長くなってから、だんだん彼の興味が薄れ最近は私ひとりで行くことが多くなっていたこと。最後にいっしょに濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』を観に行った時、私は美しい映画だと心が震えたが、彼氏の方はおもしろくないし理解できない、もうこの手の映画は観に行かなくていいと言ったこと。
平たく言えば、彼は「普通」側、私は「特別」……ではなく彼からすれば「異常」側に属する人間だということ。
細かく分類すれば私の気の遣えなさなどの小さな要因もあっただろうけれど、結局はそのような「普通」と「異常」の価値観の違いが我慢ならず、同棲はしても結婚して子どもを持つところまで考えるほどの愛情は持てなかった、それならお互い別の道を探した方が幸せになれるのでは、というのが相手の主な申し出だった。
それでも、つい昨日まで表面上は問題なく生活はできていたではないか、と私からも一応口添えはした。そちらが一方的に不満を溜めることがあるのならその原因を解消できるよう努力するし、趣味が違うことはもう仕方ないが、それぞれの趣味と時間を最低限尊重しつつ、ただ生活をともにすることだけを共通目的に成り立っている恋人や夫婦なんてごまんといる。私たちもそれではだめなのか、と。
しかし、口ではそう諭しながら、私も頭の中ではすでに現状を理解し始めていた。彼の根本的な不満の原因は互いの経験にもとづく価値観や魂の質の違いの問題であり、生活に支障が出る段階まで達していて、もうどうしようもないこと。
そして、彼だけでなく私の方も、今までの人生で形づくられた自分の性質を相手に合わせて変えようとしてまで、この生活を維持しようと思えるほどの愛情を持てなくなっていた、ということを。
私が幼少期から感じている「私がつらいと思っていることを、他の人も同じくらいつらいと思っているのか、それを確かめるすべはない」という絶望なんて、結果的に相手の益にならない限りは、きっとどうでもいいことなのだ。
はたから見ていくら幸せに見えようが、今の私の根幹にあるその絶望を人生のパートナーにないものとして扱われ、心の真ん中にずっと埋まらない穴を抱き続けることに、私はきっと堪えられない。
私が同棲を解消し実家に帰ってしばらくしたころ、楽しみに待っていた坂元裕二脚本の新作ドラマ『初恋の悪魔』が放映された。やっぱり坂元裕二の脚本はいいな、と思いながら楽しく観ていたら、とあるシーンが心に留まった。
『初恋の悪魔』には、警察署に勤める二人の主人公が登場する。一人は平凡なことを誇りに日々働く総務課職員の馬淵悠日、もう一人は挙動不審な推理オタク然とした刑事課の刑事の鹿浜鈴之介だ。二人は対照的な人物として、悠日は「普通/平凡」側、鈴之介は「特別/異常」側として描写される。
第3話で、悠日は「普通/平凡」がゆえの「特別/異常」へのコンプレックス、鈴之介は「特別/異常」がゆえの「普通/平凡」へのコンプレックスから、二人は口論になってしまう。「ただ、普通にして、普通に好きになればいいんだと思います」と悠日は言い、「普通という言葉に恐れを抱き、怯えてしまう人間は存在するんだ」と鈴之介は言う。
そしてその後、ヒロイン役の摘木星砂が、悠日にこう諭す。
「普通の人とか特別な人とか、平凡とか異常とか、そんなのないと思うよ」
「ただ、誰かと出会ったときにそれが変わる」
「平凡な人を平凡だと思わない人が現れる」
「異常な人を異常だと思わない人が現れる」
「それが人と人との出会いのいい、美しいところなんじゃないの?」
あまりにもタイミングよく、フィクションの中の人物にまんまと「救い」を提示されたので、今まで「普通/平凡」と「特別/異常」について悩んできたことが、一気にフラッシュバックする。
私が「普通」じゃないから、結婚して子どもを持つ、という世間で「普通」と見なされている希望をかなえられない。「普通」の人が当たり前にやっていることができないから。出かける時にいつも何かひとつ家に忘れものをするから。通販でよく買うものをまちがえてしまうから。面倒なことを後回しにする癖があるから。コミュニケーション能力が低いから。「特別」を諦められないことを、それらの言い訳にしているから。
でも私は「特別」にもなれない。余暇や体力をすべて投げ打つほどに何かに没頭する情熱を持てない。仕事にしているウェブデザインでさえ。文章を書くことだって、学生のころから読書量も体力も落ちてしまって小説を書く意欲も湧いてこないし、日記やエッセイにしても、淡々とした生活の中に一瞬の輝きも見出せずただ鬱屈としているだけの日常なんて書く価値がない。ましてや、こんな私でも「特別」扱いしてほしいなんて下心が見え見えの自分語りの文章なんて。ダサい。みっともない。
それでも、このまま何もせず、いつか来るかもしれない「人と人との出会いのいい、美しいところ」を感じられる瞬間を諦めるよりは、ずっとましだ。
SNSが普及して、誰もが発信する側になれる時代になった、と言われる。そのこと自体の是非はさておき、ちょっとでも能動的になれば、本当は知り得なかった人と知り合えるかもしれないという点では、確かにその通りだ。
私の日常は、文章にするほどおもしろいとは思わない。でも、他の人に関しては、ただ最近あったことを淡々とSNSでつぶやいたりPodcastで話したりしているのを見たり聞くだけでもとてもおもしろいし、SNS映えなんて気にしなくていいから、もっとその人の日常や人生のことを知りたいと思う。それと同じように、私の思う平凡な日常を「平凡だと思わない人」は、きっと世界のどこかにはいるのだろう。
だから、書く。とにかく書く。ダサくても、みっともなくても、泥水をすする思いをしてでも書く。発信するためなら手段は選ばない。今のところ、いちばん効率がいい方法が文章を書くことなのだから。「普通」でも「特別」でもない中途半端な言葉だとしても、いつか同じ周波数を持つ人のもとへ届くと信じて、宇宙へ電波メッセージを放つがごとく書き続ける。
いつだったか、私の身の上を知るとあるグラフィックデザイナーの方に、こんな予言めいたことを言われた。
「谷崎さんはいつかまた小説を書くよ」
書くという行為にも功罪はある。きっと私は人を傷つけたり、傷ついたり、承認欲求に依存しすぎて目的を見失うこともあるだろう。それに、書いたところで、幼少期からの「私がつらいと思っていることを、他の人も同じくらいつらいと思っているのか、それを確かめるすべはない」という絶望が癒えるわけではなく、何度も立ち向かっては打ち砕かれ、をずっと繰り返していくのだろう。
それでも信じている。私がこれまで、普段の生活では何の接点もない他人が書いた、たくさんの作品に生きる原動力をもらってきたように。私と同じ、「普通」でも「特別」でもないペールグレー色の魂がこの星のどこかにいて、いつかその魂のもとに私の文章が届くことを、今もまだ信じている。